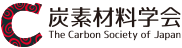2024年度の炭素材料学会学術賞、技術賞、研究奨励賞、論文賞の各賞は、規定に基づき各選考委員会の厳正な審査により選出され、会長による評議員会への報告、評議員会の承認を経て、次のように決定されました。
受賞者各位に対し、去る11月28日に開催の第51回通常総会にて表彰が行われました。会員の皆様にお知らせいたします。
学術賞
「マイクロドメイン構造論に基づいた新しい多孔質炭素製造法の開発」
宮脇 仁 氏(九州大学 先導物質化学研究所 准教授)
宮脇 仁氏は、ガス吸着に関する深い知識を活用して多孔質炭素の細孔構造の精密評価法の開発を進めつつ、炭素材料の出発物質(石炭、石油、炭化水素ガス、バイオマス、ピッチ、コークス)の物性評価や改質・調製法、多孔質炭素を含む各種炭素材料の調製法とその応用に関する研究開発を長年に渡り活発に行ってきた。同氏はその中でも特に多孔質炭素の代表格である活性炭について精力的に研究を行い、活性炭の構造モデル、調製、表面修飾の三点において重要な研究成果を上げている。
同氏は、活性炭についてマイクロドメイン構造に基づいた細孔発達機構を提案し、二種類の賦活法(ガス賦活と薬品賦活)の本質的な違いを明らかにした。二種類の賦活を行うにあたり、出発物質を共通化するだけでなく、粒子径の揃った均一な出発物質を用いたことが特筆すべき点であり、従来の研究にはない視点といえる。
同氏は、上記の細孔発達機構に関する知見を元にして、「加圧ガス賦活法(Pressurized physical activation)」を開発した。同手法を用いると常圧での通常のガス賦活では到達できない高表面積かつ高収率が達成される。加圧ガス賦活法で調製した活性炭がエタノールを冷媒に用いた吸着式ヒートポンプ(AHP)用吸着材として有望であることも見出している。これらの成果は学術的な意義が深いだけでなく産業的にも非常に価値が高いものである。
さらに同氏は選択的に特定のサイズの細孔を高機能化する表面修飾法「分子マスキング法」を開発した。この手法を発展させると細孔ごとに特定機能を付与した多機能性の表面修飾が可能であることが示唆されており、今後の発展が期待される成果といえる。同氏は、上記以外にもNMR を用いた多孔質炭素の種々の物性評価、細孔構造評価法にも重要な研究成果を上げている。したがって、同氏の業績は活性炭をはじめとする多孔質炭素の分野で先導的かつインパクトのあるものであり、炭素材料学会学術賞に値する。
研究奨励賞
「リサイクル炭素繊維の国際標準化に資する炭素繊維の評価技術に関する研究開発」
杉本 慶喜 氏(国立研究開発法人 産業技術総合研究所 主任研究員)
杉本慶喜氏は、学生時代から一貫して炭素繊維の材料力学的特性の計測および評価技術に関する研究を精力的に推進してきた。特に同氏は炭素繊維強化プラスチックのリサイクル工程から取り出される短い「リサイクル炭素繊維」の力学的特性に関する評価の重要性にいち早く気が付き、世界に先駆けてリサイクル炭素繊維1本の繊維強度分布と繊維/樹脂界面せん断強度の同時評価法を開発したことは特筆に値する。さらに同氏が開発したリサイクル炭素繊維の評価方法は、国際標準化される見込みであり、国際的にもインパクトの高い成果と言える。また、同氏は炭素繊維の到達可能強度の評価、炭素繊維1本の動摩擦力係数の評価、さらに炭素繊維の引張強度分布の評価等の研究にも取り組み、国内外の学術誌に多数発表している。
以上のように同氏は炭素繊維の力学的特性の解明といった学術的な貢献だけでなく、リサイクル炭素繊維の再利用 ・普及を通して持続可能な社会の実現にも寄与しており、同氏の業績は炭素材料学会奨励賞に値する。
論文賞
「Unveiling the hidden intrinsic porosity of marine biomass-derived carbon: Eliminating pore-blocking minerals」
Da Hea), Koji Saitob), Toru Katoc), Chika Kosugid), Takaaki Shimoharae), Koji Nakabayashia), e), Seong-Ho Yoona), e) and Jin Miyawakia), e)
(Carbon Reports Vol.2 No.3 pp.179-184に掲載)
a) Interdisciplinary Graduate School of Engineering Sciences, Kyushu University: 6–1 Kasuga-koen, Kasuga, Fukuoka 816–8580, Japan
b) Nippon Steel Research Institute Corporation: 2-6-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, Japan
c) Environmental and Process Research Department, The Japan Research and Development Center for Metals: 1-5-11 Nishishinbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0003, Japan
d)Advanced Technology Research Laboratories, Nippon Steel Corporation: 20-1 Shintomi, Futtsu, Chiba 293-8511, Japan
e) Institute for Materials Chemistry and Engineering, Kyushu University: 6–1 Kasuga-koen, Kasuga, Fukuoka 816–8580, Japan
本論文は、カーボンニュートラルな海洋バイオマスから、簡便に多孔質炭素材料を得るための新たな調製プロセスを検討した研究である。
従来の多孔質炭素材料の製造工程では、賦活処理やテンプレートの使用が必要であるが、コストと環境負荷の軽減が課題となっている。持続可能な社会の実現に向けては、低環境負荷・低コスト、かつカーボンニュートラルな資源からの新たな調製プロセスの開発が不可欠である。著者らは、高いCO2固定化能を有する海洋バイオマス(Marine biomass: MB)のわかめと昆布を炭素源として、特にMBに含まれる灰分がMB誘導炭素体の細孔構造に及ぼす影響について詳細に議論した。その結果、MBの熱分解と灰分洗浄によって、1000 m2 g-1超の多孔質炭素が得られることが明らかになった。この高い比表面積は、1) MB由来の炭素骨格に起因する細孔構造が、含有灰分の賦活効果により発達すること、2) 炭素化後の残留灰分により閉塞していた細孔が洗浄処理で開放されたこと、に起因すると結論された。さらに、灰分の洗浄方法では、水洗浄よりもCO2バブリング洗浄の方が、灰分除去効率が高く、誘導炭素内の空隙を効果的に暴露できることを明らかにした。
以上のように本論文は,持続可能な社会実現に貢献する新たな多孔質炭素材料の調製プロセスを提案し、かつ緻密なデータ解析と深い議論が行われており論文としての完成度も高い。よって、炭素材料学会論文賞としてふさわしいものと判断される。
炭素材料学会年会ポスター賞・学生優秀口頭発表賞表彰
炭素材料学会では, 2004 年(第31 回)年会より年会ポスター賞を設けています。また、2019年(第46回)より学生優秀口頭発表賞も新たに設けました。2024年(第51回)年会では学生諸君が発表したポスターおよび口頭発表を対象として, 独創性・新規性, 学術・技術的貢献度, 発表者の理解度, ポスターとしての完成度(論理展開の妥当性・読みやすさ・表現の工夫度)あるいは口頭発表スライドの完成度(論理展開の妥当性・見やすさ・表現の工夫度)などの項目について評価し, ポスター賞8件、優秀口頭発表賞6件を選考しました。ここに会員の皆様にお知らせいたします。
【ポスター賞】
辻井 太斗
信州大学大学院 総合理工学研究科 理学専攻 飯山・二村研究室
「分子形状と極性による吸着速度への影響」
藤野 研哉
北陸先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 先端科学技術専攻 後藤研究室
「ナトリウムイオン電池用ハードカーボン負極に吸蔵されたNaの低温状態における挙動解明」
笠谷 彪雅
青山学院大学大学院 理工学研究科 理工学専攻 先端素子材料工学研究室
「乱層積層CVDグラフェンへの分子修飾と電気特性評価」
山田 智也
東北大学大学院 工学研究科 化学工学専攻 渡邉研究室
「超臨界CO2を用いた活性炭細孔内へのキノン類含浸における吸着状態分析と電気化学特性評価」
近藤 宏汰
千葉大学大学院 融合理工学府 先進理化学専攻 共生応用化学コース 資源反応工学研究室
「構造制御された含窒素炭素材料の合成とCO2吸着への応用」
李 新鈺
大阪大学大学院 基礎工学研究科 物質創成専攻 西山研究室
「無機塩添加無溶媒法におけるメソポーラスカーボンの細孔構造制御」
算用子 晃哉
岩手大学 理工学部 化学・生命理工学科 化学コース 表面反応化学研究室
「黒鉛層間を利用した硫化モリブデンナノシートの調製」
池田 勇樹
兵庫県立大学大学院 工学研究科 応用化学専攻 応用物理化学研究グループ松尾研究室
「マグネシウム電解液におけるグラフェンライクグラファイトの電気化学的挙動(2)」
楊 欣然
大阪大学大学院 基礎工学研究科 物質創成専攻 西山研究室
「Effortless synthesis of N,P co-doped carbon nanosheets for hydrogen evolution reaction: experimental quantitative analysis and DFT calculation corroboration.」
【優秀口頭発表賞】
高濵 聡汰
長崎大学大学院 総合生産科学研究科 共生システム科学コース 化学・物質科学分野 応用物理化学研究室
「Mgイオンの状態解明に基づくEDLC用多孔性炭素電極の設計」
大倉 健太郎
岡山大学大学院 環境生命自然科学研究科 応用化学専攻 仁科研究室
「ホウ素の結合状態を精密に制御したカーボンの合成:アルカリイオン貯蔵性能の評価」
熊野 圭悟
横浜国立大学大学院 理工学府 化学・生命系理工学専攻 窪田・稲垣研究室
「アントラキノンを固定化した酸化グラフェンの電気化学的CO2吸脱着システムへの応用」
張 夢璇
東北大学大学院 工学研究科 化学工学専攻 西原研究室
「Efficient synthesis of hydrophobic graphene quantum dots via low-temperature chemical vapor deposition on TiO2」
網野 柚貴
名古屋工業大学大学大学院 工学研究科 工学専攻 生命・応用化学系プログラム 川崎・石井研究室
「SnO2/g-C3N4複合体の光触媒的エストロゲン分解」